前回は話がKopiと脱線してごめんなさい💦今日はシンガポール国立大学(NUS)についての話。
MBA受験を進める中で、シンガポールにはいくつか有名なMBA校がある。NUS、NTU、SMU——。
でも正直に言うと、僕がNUSを選んだ理由はとてもシンプルだ。先輩が行っていて、話がめちゃくちゃ面白かったから。
先輩との出会いについては過去のブログで簡単に触れてます。
先輩が語った“理想のNUS”はめちゃ眩しかった
「授業はほとんどグループワークだよ」
「イスラエルの提携校に留学して、アグリテックの現場を見た」
「ヨーロッパ企業を訪問して、最先端の経営を体感した」
…って、どれもキラキラしすぎてた。当時の僕は「イスラエル=テクノロジー?」ってピンとこなかったけど、
話を聞くうちに、NUSって“座学じゃなくて現場で学ぶMBA”なんだと感じた。
そしてその勢いのまま、僕はNUSに応募することを決めた。「なんかここ、面白そう」って。
で、実際どうだったかって?
入学して最初のグループワークで悟った。現実はぜんぜん甘くない!!
グループワークが始まると、英語の嵐が吹き抜けた。インド人、フランス人、中国人、インドネシア人。
誰も待ってくれない。話すテンポも、笑うタイミングも、すでにプロ級。みんなの発言が流れるように飛び交う中で、僕だけ“うんうん”って頷きながら、実はほぼ理解ゼロ。いわゆる「笑ってるけど内容わかってない人」の完成形だった。
シンガポールで英語使って働いてたし、そこそこやれると思ってた。
でも、マーケティングやアカウンティングなど僕の専門分野でない科目について、ディスカッションを英語で瞬発的にやるって、
もう脳がフル回転どころか、ショートして煙出てた。💨
NUSのアドミがミスって僕を合格させたんじゃ…?マジでそう思った。
全員が話してる英語が速すぎて、「Sorry, can you repeat?」を言う勇気すら出なかった。
そのとき思った。MBAって“知識を学ぶ場所”じゃなく、“自信を失っても前に出る練習場”なんだと。
それでも僕を支えてくれた仲間
ある日、グループワークの途中で完全に心が折れかけていた。
英語でうまく発言できず、チームメイトが議論をどんどん進めていくのを横で見ながら、「もう僕、いらないんじゃないか」と思ってた。
そんな僕に気づいたのが、同じチームのインドネシア人、Yuliusだった。彼は僕に声をかけてくれた。
“We are in the same boat.”
みんな同じ船に乗ってるんだ、一緒に頑張ろう、一人じゃないよ。その一言が、不思議なくらい心に刺さった。
それから少しずつ、恐れよりも「チームのために発言しよう」という気持ちが勝つようになった。
間違えても、噛んでもいい。仲間がちゃんと聞いてくれる。それが、僕にとってのNUSの一番の魅力だった。
まとめ
NUSのMBAを目指す前、先輩の話は本当に華やかに聞こえた。
イスラエルでのテクノロジー、ヨーロッパ企業訪問、グローバルな議論。
そのどれもがキラキラして見えて、僕もあんな風になれる気がしていた。
でも実際のNUSのMBAは、もっと泥臭くて、もっと人間臭い。
完璧なプレゼンより、噛みながら話した勇気。教授の質問が理解できず、的外れな回答をとりあえずしてしまった恥ずかしい経験。
挑戦して、落ち込んで、励まされて、また立ち上がる。それを何回も何回も繰り返す。
NUSで過ごした3年間は、挑戦の痛みと、仲間の温かさの両方を教えてくれた。
あの時、先輩の話を「面白そう」と思って選んだのは、やっぱり正解だったと思う。

Mr. “We are in the same boat!!”
👉 次回予告|Vol.17
応募書類は英語スコアだけじゃない
CV(職務経歴書)とエッセイは、いわばあなた自身のドキュメンタリー。数字や肩書きだけじゃなく、どんな挑戦をして、どう成長したか。そして、MBAで何を得て、どんな未来を描いているのか。スコアでは伝わらない“生きたストーリー”をどう言語化できるかが勝負。
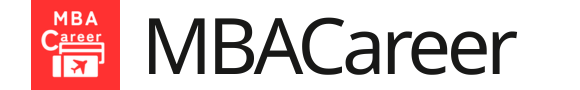


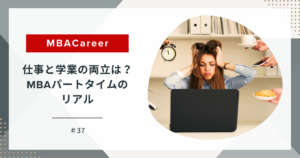
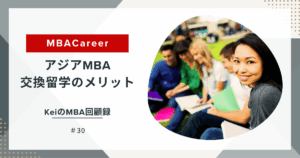

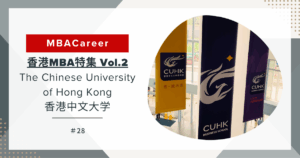


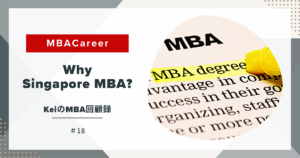
コメント